 第一回 第一回  第二回 第二回  第三回 第三回 第四回 第四回 第五回 第五回 第六回 第六回 第七回 第七回 第八回 第八回 第九回 第九回
 第十回 第十回 第十一回 第十一回  第十二回 第十二回 |
| 第四回滑稽俳句協会報年間賞決定! |
|
| |
 |
神奈川県 下嶋四万歩 |
|
| 秋行くや七人の敵六人に |
|
| 受賞の感想 |
このところ、夏バテ気味で、あまり調子が良くない状態にあったところでの年間賞の受賞の報せに、思わず快哉を叫びました。
近頃、痛切に感じることは、移りゆく時の疾さです。「時の流れのままに」とは言いながら、まさに坂を下り落ちるごとく過ぎゆく歳月に驚かされ、これじゃあ付いてゆけない、というのが実感です。
そんな中、かつての仇敵(?)達が、ひとり消え、また、ひとり去りゆきました。こんな時こそ、哀愁を帯びた滑稽俳句作成の好機と捉え、受賞句をものにしました。
そして今また、「明日からは汗のかかない人送る」。
この度の受賞は、萎えた私の気持ちに、八木会長が気合の喝を入れてくださったものと受け止めています。というわけで、これからも、しこしこ、とぼとぼ、句作の道を辿りゆかんと、心新たにしている次第です。
ありがとうございました。
|
|
| |
| |
 |
兵庫県 金澤 健 |
|
| 卒業や恩に気付かぬ顔ならべ |
|
| 受賞の感想 |
常々、五七五句による表現方法は、実に多様な事柄を描けると考えております。自然事象、人間の本質、人情の機微、社会の矛盾や仕組み、等々です。(大雑把に言えば、自然、人間、社会の三つが主たる対象になろうかと思います)
前回は、ふぐの値段が高過ぎるという社会時評、「ふぐ料理毒よりこはき時
価の文字」の句で賞を頂きました。今回は、人間社会の一断面を皮肉る句が評価して頂けたこと、非常に嬉しく思っています。
実は今、私が真剣に取り組んでおりますのは〝自然の情景をありのままに表現し、尚且つ、おかしみが感じられる句を詠む〝ことであります。
出来得れば、花鳥諷詠句で、何時の日か滑稽俳句年間賞「天」を頂ければと思い、精進を続けてまいります。
自然、社会、人間、森羅万象全てを詠み、句を読まれる方と滑稽の感動を分かち合いたいと切に願っております。
今後とも、宜しくお願い申し上げます。
|
|
| |
| |
 |
愛媛県 梅岡菊子 |
|
| 切干と呼ぶ大根のなれのはて |
|
| 受賞の感想 |
滑稽俳句の素晴らしさは、自身の脳裏に浮かんだ「詩」の断片を膨らませイメージすることで即ち俳句になることです。句材はいくらでも身辺に見つけることができるのですから、吟行しなくても句作ができ、これが滑稽俳句の魅力の一つでもあります。
この句の経緯を振り返ってみます。最初に「切干」がありました。もとはと言えば立派な大根だった。それが似ても似つかぬものに変身した。そう思ったときに「なれの果て」という言葉が浮かびました。「大根を無意識に擬人化」した句であることに気づきました。
八木会長が常々、滑稽句の基本は擬人化にあると説かれています。そして「なれの果て」という表現です。「俗」な言葉です。マイナス的表現です。伝統俳句では使われないだろう「卑俗」な言葉を使うことで、おどけて見せたのです。この句で私は「滑稽句」づくりの方法に手応えを感じています。大変な賞をいただき、今後、受賞者として恥じない句をつくり続けようと思います。
|
|
|
| |
| |
| 選 評 滑稽俳句協会会長 八木健 |
「天」…男は外に出たら七人の敵がいるとされる。なるほど会社の同期入社は競争相手だから敵であり、蹴落とされる場合もある。しかし、定年退職すれ
ば七人の敵は懐かしい戦友。「秋行く」の季語に一人減り、二人減りする寂しさを取り合せて描いた。敵こそが大切な存在だったと分かる年齢になったのだ。
「地」…卒業という格調ある季語に、「恩に気付かぬ」という不道徳な卒業子を並べて裏切った可笑しさが見事。卒業歌も「わが師の恩」に感謝する歌詞の類は絶滅危惧種らしい。師の恩、親の恩と特定してはいないが、そこは読者にゆだねられている。時代を描くのも俳句の役目の一つであるが、この句には「平成」が記録された。
「人」…切干大根を写生しての句だが、作者は「大根のなれのはて」と感じた。「なれのはて」を「切干大根」という立派な名をつけて持ち上げていることが可笑しいとも気付いた。俳句は「ひねる」ものである。所詮、切干は、かつては瑞々しく豊満であった大根の「なれのはて」とからかったところが「ひねり」である。俳句の滑稽は「俗」にあるが、「なれのはて」が効いている。
|
|
| |
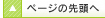 |